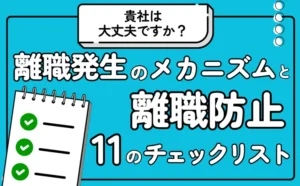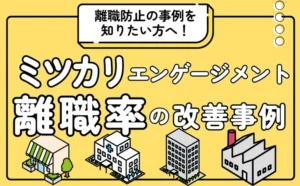早期離職対策に行政の支援施策を活用しよう!
人材採用市場では企業間の競争が激化しており、目標人員を確保できない企業が増えてきています。人員確保に苦しむ企業は、採用活動の目的が「人員を埋めること」に集中してしまい、内定者や新入社員へのフォロー体制がおろそかになりがちです。
内定者や新入社員へのフォローがおろそかになると浮かび上がってくるのが、早期離職の問題です。早期離職とは、一般的に入社から3年以内の離職のことで、大卒の新入社員の早期離職率は直近30年で平均3割を超えています。
長らく改善されていない早期離職の問題に対して、雇用維持関係や人材確保等支援助成金など、行政は様々な施策を打ち出しています。
今回の記事では、数ある行政の施策の中から、東京都が公開している「早期離職防止ガイドブック」の内容について紹介します。
早期離職防止ガイドブックとは?
早期離職防止ガイドブックとは、公益財団法人東京しごと財団/東京しごとセンター・ヤングコーナーが発行している「早期離職を防ぐ」ことを目的としたガイドブックです。
早期離職防止ガイドブックの内容は、特に中小企業の経営者・人事担当者を対象としたものになっています。採用や人材育成だけでなく、より働きやすい職場環境をどのように作るのか、コミュニケーションはどうとれば良いのかなど、導入が容易な「すぐに始められること」をたくさん取り扱っています。
早期離職防止ガイドブックの内容とは?
早期離職防止ガイドブックの内容は、3つの巻頭企画、6章の本編、Q&Aで構成されています。面接評価シートやOJT計画シートなど、採用・教育の現場で使えるチェックシートが付いており、巻末には国や東京都が運営する各種研修・セミナー・相談場所などの施設・機関の連絡先が記載されています。
全体の構成としては、若手社員の離職理由や思考傾向など、早期離職の原因を知るためのアンケート調査結果が序盤で示されます。早期離職の原因を踏まえた上で、採用面接・育成計画・OJT・職場環境のケアなどの方法について言及され、入社から定着に至るまでの広範囲にわたるトピックが網羅されています。
早期離職防止ガイドブックの本編は、以下の6つの章で構成されています。
- いまどき若手社員の傾向を理解する
- 採用から入社後の育成まで連携して取り組む
- 経営者が知っておくべき、企業と人材のための育成計画
- 本気で取り組むOJT
- 見落とさない。職場の人間関係
- 職場定着につながる制度整備と心のケア
早期離職防止ガイドブックの内容を簡単にご紹介!
早期離職防止ガイドブックは、冊子版で64ページ、PDF版で34ページとなっています。早期離職の防止に役立つ内容ばかりなので、すべて読んでいただくのが一番良いのですが、日々の業務が忙しくなかなか時間が取れない方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、忙しい人事担当者様のために、早期離職防止ガイドブックの概要を簡単にまとめてご紹介します。全文を知りたい方は、東京しごとセンター・ヤングコーナーのホームページでPDF版が公開されておりますので、そちらをご覧ください。
参照『東京しごとセンター・ヤングコーナー』早期離職防止ガイドブック
本編1章、若手社員とのコミュニケーション方法について
早期離職防止ガイドブックの本編1章は「いまどき若手社員の傾向を理解する」というテーマで構成されており、育成担当と若手社員のコミュニケーションの取り方のアドバイスが記されています。
最近の若手社員の特徴を「指示待ち型」「リスク回避型」「自分基準型」の3タイプに分けて分析し、それぞれに対する経営者や育成担当者の接し方の例が丁寧に解説されています。
早期離職の理由は、上司や同僚との人間関係がもっとも多い原因として挙げられているため、若手社員への接し方を知っておくことは早期離職を防止する上で非常に重要です。
本編2章、採用活動における雇用のミスマッチ防止について
早期離職防止ガイドブックの本編2章は「採用から入社後の育成まで連携して取り組む」というテーマで構成されており、採用活動を成功させるための方法が記されています。
早期離職の主たる原因の1つとして「入社前後でのギャップ」すなわち「雇用のミスマッチ」が挙げられます。給与や休日などの労働条件だけでなく、人間関係や価値観、働いてみないと分からない労働環境の実態など、様々な要因が早期離職を引き起こします。
雇用のミスマッチ防止は、入社前後のギャップを起こす要因を潰すために行います。本編2章では「雇用のミスマッチはなぜ起こるのか」という根本的な問題に着目して、ミスマッチが起こった理由の調査データや新卒採用と中途採用の特徴などがまとめられ、対策方法が提示されています。
本編3章・4章、人材の育成方法について
早期離職防止ガイドブックの本編3章は「経営者が知っておくべき、企業と人材のための育成計画」、4章は「本気で取り組むOJT」というテーマで構成されており、人材の育成方法について記されています。
中小企業では人事まで手が回らず、経営層の独断で感覚的に採用や配属が行われるというケースが少なくありません。早期離職防止ガイドブックの本編3章と4章では、人材の育成計画がなぜ必要なのか、具体的にどのように育成計画を立てていくのか、OJTはどうすべきなのかの助言が細かく掲載されています。
早期離職が多い企業では、若手社員が育たず、中堅以上の社員が少ないという傾向が見られます。人材の育成計画やOJTの運用方法をしっかり組み立てておくことで、早期離職の防止だけでなく、新入社員の成長促進やモチベーション向上にも役立ちます。
本編5章・6章、人間関係や職場環境の改善方法について
早期離職防止ガイドブックの本編5章は「見落とさない。職場の人間関係」、6章は「職場定着につながる制度整備と心のケア」というテーマで構成されており、人間関係や職場環境の改善方法について記されています。
早期離職の理由で特に多く挙げられるのが「人間関係が合わなかった」という原因です。早期離職防止ガイドブックでは、5章と6章の2項目にわたって、コミュニケーションの取り方や働きやすい環境づくりについての提言がなされています。
良好な人間関係を作れるかどうかは、上司にかかっていると言っても過言ではありません。良好な人間関係を構築するために参考にしたいのが、PDF版49ページに記されている「育成につながる褒め方・叱り方」です。「なぜ褒める」「なぜ叱る」という根本的な問いから始まり、社員の成長につながる接し方が端的にまとめられています。
良好な職場環境を整備する方法としては、新入社員の定着率を向上させるための施策や、メンタルヘルス対策の取り組み方について詳細にまとめられています。PDF版57ページでは、昨今特に注意したいハラスメント行為への対策や、社員のモチベーションを保つための制度整備などについても記されています。
早期離職防止ガイドブックを活用して定着率向上を図ろう!
早期離職防止ガイドブックとは、公益財団法人東京しごと財団/東京しごとセンター・ヤングコーナーが発行している「早期離職を防ぐ」ことを目的としたガイドブックです。
早期離職防止ガイドブックでは、若手社員とのコミュニケーション方法から職場環境の改善方法まで、様々な角度から早期離職を防止する方法が記されています。早期離職防止ガイドブックの内容を一度に実現することは難しいですが、会社にとって致命的な問題となる早期離職に対策するためには、課題を一つひとつ解決していく姿勢が大切です。
自社の早期離職率を改善するためには、いきなり新制度の導入や組織体制の改革などの大掛かりな取り組みから始めるのではなく、若手社員へのコミュニケーション方法や褒め方・叱り方の改善など、すぐにできるコストのかからない対策から始めていくとよいでしょう。
貴社は大丈夫ですか?離職が発生するメカニズムと離職防止のための11のチェックリスト
多くの企業が人手不足に陥っている一方で、少子化などの影響で求人倍率が増加傾向にあります。これは求人に対して、求職者の数が年々足りなくなっていることを物語っています。
人手不足の背景から、日本の多くの会社が従業員の離職にて甚大なダメージを受けています。あなたの会社は従業員の離職防止に努めているでしょうか?
今回は、どの会社でも悩んでいる従業員の離職について、既存従業員の離職を防ぐ方法や辞めない人材を採用する方法、離職を防ぐチェックリストとしてまとめました。是非ダウンロードしてご参照ください。
>>貴社は大丈夫ですか?離職が発生するメカニズムと離職防止のための11のチェックリスト
離職防止の事例を知りたい方へ ミツカリエンゲージメントを活用した離職率の改善事例集
近年、離職防止・生産性の向上・組織課題の可視化を目的に、エンゲージメントサーベイを活用する企業が増えています。一方で「エンゲージメントサーベイを初めて導入するため、活用イメージが持てていない」「過去に失敗した経験がある」といった声も少なくありません
今回は、ミツカリエンゲージメントを実際に導入し、エンゲージメント向上や自社の課題解決に成功した企業様の活用事例をまとめました。自社の課題や導入の背景、具体的な成果などを掲載していますので、より実践的な活用イメージを持っていただける内容となっています。
「エンゲージメントサーベイを計測だけで終わらせない」ためのヒントを知りたい方は、ぜひ資料をご覧ください!
>>離職防止の事例を知りたい方へ ミツカリエンゲージメントを活用した離職率の改善事例集
離職での損失額が分かる 離職コスト算出シミュレーター
若手社員の離職が続き、『見えないコスト』に悩んでいませんか?
多くの企業が、採用や研修にかかる直接的な費用だけでなく、企業の成長鈍化や競争力低下に繋がる大きな損失を見過ごしがちです。貴社の離職が一体いくらの損害になっているのか、その『目安』を把握することが、経営改善の第一歩です。