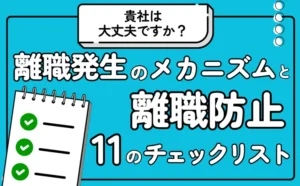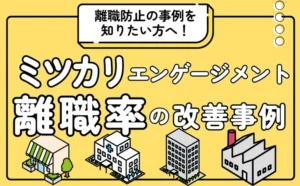日本の少子高齢化と労働力人口
日本では、人口減少に伴う人手不足が深刻な問題となっています。
総務省統計局の人口推計によると、総人口のピークは2008年で、2010年以降は減少し続けています。15歳~64歳の人口も平成7年(1995年)の8,726万人がピークであり、2010年からは減少し続けています。15歳~64歳の人口は、平成7年が8,726万人であったのに対し、平成30年では7545万人となっており、1,000万人以上減少しています。

出典元『総務省統計局』人口推計 2018年(平成30年)10月1日現在 概要
しかし総務省統計局の労働力調査によると、15~64歳の労働力人口は2018年平均で5955万人と、前年に比べ56万人増加していることがわかります。特に女性は51万人という大幅な増加となっており、女性の社会進出などによって労働力人口が増加傾向にあることがわかります。

出典元『総務省統計局』労働力調査(基本集計)平成30年(2018年)平均(速報)
昨今、大企業でも労働力が足りていないため、積極的な採用を行っています。中小企業から大企業への転職者数も増加傾向にあり、中小企業での人手不足がより深刻化しています。
今回は、近年増加している「人手不足倒産」について、その推移を説明します。
人手不足倒産とは?推移はどうなっているのか
人手不足倒産とは、人手が不足することで会社が倒産することを指します。
以前から、運輸業や医療・福祉関連・建設業などを中心に人手不足の深刻化は問題となっていました。中小・零細企業を中心に人手不足倒産は相次いで発生しており、今後も増加するとみられています。
事業継続に必要な社員やアルバイトを確保できない、後継者不足など、人手不足倒産には様々な背景があるため、原因や対策は一様ではないところに注意が必要です。
人手不足によって倒産が起こる原因や理由について
人手不足によって倒産が起こる原因や理由を以下にあげます。
新たな雇用を確保できない
少子高齢化により働き手が減少しており、どの企業もいかに優秀な人材を確保するかを重要視しています。採用しようとしてもすでに他社に雇用されているなど、即戦力となる優秀な人材を獲得することは困難です。
業績が好調で多くの注文がはいったとしても、それに充分に応えられる商品やサービスを提供することができなければ、結局は仕事を受けられず、売上げは低下していきます。人材募集に十分な資金を割けない中小・零細企業ほど、人手不足を理由とした倒産が起きやすくなります。
人材流出による人手不足
先ほども述べたように、どの企業もいかに優秀な人材を確保するかを重要視しています。そのため、優秀な人材であれば他社も引き抜きたいと考えています。それまで社内で中心的に働いていた社員が転職する、あるいは独立する、といったことで業務を正常に行えなくなれば、事業継続が不可能になるケースがあります。
一般的な人材であっても退社が続くとなると、新たな人材の確保が難しい昨今、すぐに人手不足に陥ります。残った社員に業務負荷がかかり、さらに離職に歯止めがかかりにくくなります。
人材の流出と補強が進まない負のスパイラルの中では、人手不足倒産の危険性は大きくなるでしょう。
人手不足による人件費の高騰
近年、少子高齢化により働き手が減少しています。労働力人口は増加傾向ですが、外国人人材や女性、定年後の再雇用などの未活用人材の増加が理由です。彼らを採用して定着させるためには、時短勤務などの柔軟な対応が求められます。福利厚生制度を整える余裕のない零細企業や中小企業は、彼らの採用がうまくできないために人手不足に陥ります。
また働きたい人と雇いたい企業側のミスマッチが起こっているのが原因と考えられます。労働力人口増加の恩恵を受けられていない企業の特徴としては、「フルタイムで働いてほしい」「突発的な残業にも対応してほしい」「日本人とうまくコミュニケーションをとって欲しい」などの採用要件を掲げがちです。「採用したくても、希望する人材が集まらない」というジレンマが、人件費の高騰を招いています。
仮に採用がうまくいったとしても、収支のバランスが悪化してしまい、倒産という形になる恐れがあります。
人手不足による人材育成の壁
離職が多く、雇用が安定しない企業では、総じて人材育成は難しくなります。
社内で中心的に働いていた社員が離職した場合、技術やノウハウは途切れてしまうだけでなく、新たに雇用した人材を教育する社員も不足することになります。教育専門の部署や人材を配置する余裕のない中小企業では、人材育成まで手が回らないのが現状でしょう。
新人社員も十分な教育のないまま現場に送り出されることになり、正常な業務を期待することは難しくなります。そういった職場環境では、せっかく雇用してもすぐに離職してしまうという事態になりかねません。
人材不足は中核社員にとって、新人教育の手間や自身の業務遂行に支障がでるだけでなく、自身のスキルアップや成長にとっても問題となります。そのため企業からすると、経営に携わる人材が育たないといった問題を引き起こします。
人手不足は人材育成を困難にし、果ては事業継続を困難にしてしまうのです。
人手不足倒産の件数とその推移
帝国データバンクの調査によると、2019年度の人手不足倒産は185件発生し、前年度から比べると48.2%増加していることがわかります。調査開始以降、人手不足倒産は右肩上がりで推移しています。

出典元『帝国データバンク』2019 年の人手不足倒産、4 年連続で最多を更新
倒産件数自体は、過去数年で大きな変化はありません。人手不足倒産の件数は増加していることから、業績悪化による倒産よりも人手不足による倒産の割合が増加していることが読み取れます。

出典元『独立行政法人 労働政策研究・研修機構』国内統計:企業倒産状況
2018年度の倒産件数は、全体では前年度を下回った一方、人手不足倒産は大幅増となったことがわかります。
従業員の待遇改善や最低賃金の引上げなどで賃上げを実施する企業が増えるなか、高待遇での採用が困難な企業や人件費上昇分を転嫁できない企業を中心に倒産が目立っています。
今後、人手不足倒産は増加するのか?
政府は人手不足が深刻化している問題に対し、外国人材の受け入れ拡大を促す法改正を行いました。今後、こうした法改正効果などが期待されるものの、小規模企業を中心に人手確保が難しい状況が続くと予想されます。
現在、中小企業から大企業に転職する人は増加傾向にあります。先行きが不透明な現代において、会社の倒産は従業員の生活を一変させることは言うまでもありません。外部環境の変化を受けやすい中小企業で働く人たちが、自社の将来性を気にかけ大手企業への転職を考えることは、当然の成り行きかもしれません。
転職希望者とって、現在は売り手市場です。少子高齢化による労働力人口の減少は明らかですし、女性や高齢者、外国人労働者の社会進出を考慮に入れても、求職者優位の状態はなかなか覆らないでしょう。転職や独立による人材流出、それに伴う人材確保の困難さは、今後も改善されることは難しいと考えられます。求職者優位の状態から、人件費の高騰も続くと予想されます。
企業側がブランディングなどの努力を行えば、求職者優位が続く状況に陥ることは避けられます。「この会社で働きたい」と大多数の求職者が思える企業であれば、離職による人材の流出、求職者と雇用側のミスマッチによる採用難、人件費にかかる費用は、ある程度抑えられるでしょう。
後継者の不足も人手不足倒産の一因です。経営者が、自身の子や孫に事業を引き継ぎたいと考えていても、本人にそのつもりがなくては元も子もありません。日本経済・社会という大きな枠組みで考えれば、雇用、技術・ノウハウを残す、従業員の生活を守るといった観点でも、後継者不足による倒産は避けたほうが賢明です。そのためにも中核となる社員の人材育成に力を入れることが重要となります。
後継者は、自身の子や孫でなくてはならない、といったことはありません。M&Aといった方法で会社を残すことも可能なため、早くから会社存続の道を探ることが大切です。
自社だけでも取り組める課題はあるものの、社会として根本となる原因を解消しなければ、人手不足倒産の増加傾向は続くと考えられます。
人手不足倒産にならないために取り組むべきこと
人手不足倒産とは、店舗運営などの業務を回す人材が不足するために起こるだけではありません。次期管理職や経営層などのコア人材が不足することでも引き起こる倒産なのです。
人手不足倒産は増加傾向にあり、社会として根本となる原因を解消しなければ増加傾向は続くと考えられます。
人手不足倒産を社会の問題として丸投げするのではなく、自社だけでも取り組める課題はあります。短期的に人手不足を解消する方法を取るのか、中長期的な目線で人手不足を解消するのか、目的や施策を明確にして取り組んでいく必要があります。
貴社は大丈夫ですか?離職が発生するメカニズムと離職防止のための11のチェックリスト
多くの企業が人手不足に陥っている一方で、少子化などの影響で求人倍率が増加傾向にあります。これは求人に対して、求職者の数が年々足りなくなっていることを物語っています。
人手不足の背景から、日本の多くの会社が従業員の離職にて甚大なダメージを受けています。あなたの会社は従業員の離職防止に努めているでしょうか?
今回は、どの会社でも悩んでいる従業員の離職について、既存従業員の離職を防ぐ方法や辞めない人材を採用する方法、離職を防ぐチェックリストとしてまとめました。是非ダウンロードしてご参照ください。
>>貴社は大丈夫ですか?離職が発生するメカニズムと離職防止のための11のチェックリスト
離職防止の事例を知りたい方へ ミツカリエンゲージメントを活用した離職率の改善事例集
近年、離職防止・生産性の向上・組織課題の可視化を目的に、エンゲージメントサーベイを活用する企業が増えています。一方で「エンゲージメントサーベイを初めて導入するため、活用イメージが持てていない」「過去に失敗した経験がある」といった声も少なくありません
今回は、ミツカリエンゲージメントを実際に導入し、エンゲージメント向上や自社の課題解決に成功した企業様の活用事例をまとめました。自社の課題や導入の背景、具体的な成果などを掲載していますので、より実践的な活用イメージを持っていただける内容となっています。
「エンゲージメントサーベイを計測だけで終わらせない」ためのヒントを知りたい方は、ぜひ資料をご覧ください!
>>離職防止の事例を知りたい方へ ミツカリエンゲージメントを活用した離職率の改善事例集
離職での損失額が分かる 離職コスト算出シミュレーター
若手社員の離職が続き、『見えないコスト』に悩んでいませんか?
多くの企業が、採用や研修にかかる直接的な費用だけでなく、企業の成長鈍化や競争力低下に繋がる大きな損失を見過ごしがちです。貴社の離職が一体いくらの損害になっているのか、その『目安』を把握することが、経営改善の第一歩です。