
従業員満足度調査(ES調査)おすすめ比較|目的別・機能別で選ぶポイント解説
働き方の多様化やリモートワークの普及により、社員の満足度や会社への愛着を把握することは、ますます難しくなっています。「社員の不満や課題に気づけず、離職につながってしまった」「部署ごとに満足度の差が大きく、改善施策がうまく進まない」といった悩みは、多くの企業で共通しています。
こうした課題に対して注目されているのが、従業員満足度調査(ESサーベイ)です。社員の仕事や職場環境への満足度を定量的に把握することで、組織の状態を客観的に可視化。改善すべきポイントを明確にすることで、離職防止や生産性向上など、具体的な施策につなげることが可能です。
一方で、従業員満足度調査には種類や規模、機能、コストの違いがあり、「自社に合うサービスはどれか」「導入後に実際に活用できるか」と悩む企業も少なくありません。
本記事では、主要な従業員満足度調査サービスの比較ポイントや活用シーンを整理し、企業が自社に最適なサービスを選ぶ際の参考になる情報を提供します。従業員の声を正しく把握し、組織改善に活かす第一歩として、ぜひご活用ください。
目次
従業員満足度調査(ESサーベイ)とは?
従業員満足度調査(ESサーベイ)とは、社員が「働く環境や待遇にどれだけ満足しているか」を定量的に測定する調査です。給与や福利厚生、職場環境、上司との関係性など、従業員が日々の仕事で感じる満足度を把握できるのが特徴です。
たとえば、社員が「職場環境に満足している」「上司との関係が良好」と感じていれば、定着率やモチベーションの維持につながります。一方で「業務環境に不満がある」「評価が不透明だ」と感じる場合、満足度が低下し、離職リスクや業務パフォーマンスの低下につながる可能性があります。
従業員満足度調査の目的とは
企業が持続的に成長するためには、社員がどのような気持ちで働いているかを正しく把握し、環境や制度を改善していくことが欠かせません。そのために導入されるのが従業員満足度調査です。 主な目的は以下の通りです。- 離職防止・定着率向上 従業員の不満やストレスの兆候を早期に把握し、改善策を打つことで優秀な人材の流出を防ぎます。
- 生産性・パフォーマンスの維持 社員の満足度を把握することで、やる気や集中力の低下を防ぎ、組織全体の成果につなげます。
- 職場環境・制度改善 従業員の声をもとに、オフィス環境や評価制度、福利厚生の見直しを行うことで、働きやすい職場づくりを支援します。
- マネジメント支援 部署やチームごとの満足度の差を可視化し、管理職が適切にフォローできる体制づくりを後押しします。
エンゲージメントサーベイとの違い
従業員満足度調査は、社員が働く環境や待遇にどれだけ満足しているかを測ることが中心です。「給与・福利厚生」「職場環境」「上司との関係性」など、日々の働きやすさを可視化することが目的です。満足度が高ければ定着率向上や業務の安定につながりますが、必ずしも社員の主体的な貢献意欲や組織への熱意には直結しません。 一方、エンゲージメントサーベイは、社員が組織や仕事にどれだけ前向きに関与しているかを測ります。「会社の成功を自分ごととして捉える」「働きがいを感じている」といった組織への熱意や主体的な貢献意欲が中心であり、生産性や業績、離職率との関連性がより強いのが特徴です。
簡単に言えば、従業員満足度調査は「働く環境の快適さ」を測る体温計、エンゲージメントサーベイは「仕事や組織への熱量」を測るエンジンの計器のような役割です。企業は両者を組み合わせることで、社員の働きやすさと働きがいを両立させ、より強い組織をつくることができます。
従業員満足度調査(ES調査)を選ぶときのチェックポイント
従業員満足度調査は、社員の働きやすさや職場環境への満足度を可視化し、組織改善につなげる重要なツールです。しかし市場にはさまざまな種類の調査があり、単に「有名だから」「低コストだから」といった理由で選ぶと、自社の目的に合わず効果が出ないこともあります。
ここでは、導入時に押さえておきたいチェックポイントを解説します。
1.測定項目の妥当性
従業員満足度調査(ES調査)を導入する際、最初に確認すべきポイントのひとつが「測定項目の妥当性」です。ES調査は、設問の内容や視点によって把握できる情報が大きく変わるため、自社が知りたいことと調査内容が一致しているかを慎重に確認することが重要です。 ES調査の設問は大きく分けて以下のようなタイプがあります。
- 待遇・環境に関する項目
- 給与や福利厚生、勤務環境、労働時間やオフィス環境の快適さなど、社員が日常的に感じる働きやすさや満足度を測定する設問です。職場環境改善や制度見直しのヒントを得るのに適しています。
- 人間関係・制度への満足度を測る項目
- 上司や同僚との関係性、評価制度やキャリア制度への満足度、チーム内コミュニケーションの質など、社員が感じる組織内の人間関係や制度面の満足度を可視化できます。マネジメント改善や組織文化の向上に役立つ情報を得ることができます。
- 理論的尺度に基づく設問
- eNPS(従業員推奨度)など、学術的・理論的に信頼性のある指標に基づく設問もあります。こうした設問は、他社比較や定量的な評価、長期的な傾向分析に活用しやすく、データの客観性を高める役割があります。
調査の目的に合わせて、どのタイプの設問を重視するかを明確にすることが、ES調査の効果を最大化する第一歩です。例えば、職場環境の改善が課題であれば待遇・環境系の設問を重視し、組織内コミュニケーションや評価制度の改善が狙いであれば、人間関係・制度系の設問に重点を置く、といった判断が必要です。
調査項目の妥当性を確認することで、ES調査の結果が「ただの数値の羅列」にならず、具体的な改善策につながる有益な情報として活用できるようになります。
2.回答のしやすさ
従業員満足度調査(ES調査)の最大の目的は、社員の率直な声を引き出し、組織改善や制度設計に役立てることです。しかし、どんなに設問が精緻で理論的に優れていても、社員が回答しにくい設計であれば、得られるデータの精度や活用効果は大きく損なわれます。
そのため、調査を選ぶ際には「回答のしやすさ」が非常に重要なポイントとなります。具体的には、以下の点に注意して設計されているかを確認しましょう。
- 設問数と回答時間
- 長すぎる設問は途中で離脱する原因になります。
- 質問形式の工夫
- 自由記述だけでなく、選択肢形式やスコア形式を用いると、社員が回答しやすく、分析もしやすくなります。
- アクセス性
- PCやスマートフォン、タブレットなど、さまざまな端末から回答可能か
- フィードバックと活用イメージの提示
- 調査結果が「組織改善に役立つ」と社員自身が理解できれば、回答意欲は格段に高まります。
回答のしやすさは、調査の精度や信頼性に直結します。設問の数や形式、アクセスのしやすさ、活用イメージの提示など、社員がストレスなく回答できる仕組みが整っているかどうかを確認することが、ES調査の成果を最大化するカギです。
3.分析機能の充実度
従業員満足度調査(ES調査)は、単にアンケートを回収して終わりでは意味がありません。社員の声を「見える化」し、そこから課題を抽出して改善につなげてこそ、調査を実施する価値があります。
そのためには、収集したデータをどれだけ使いやすく分析できるかが大きなポイントになります。
- データの可視化
- 回答結果が数字の羅列だけでは、担当者や経営層が理解するのに時間がかかります。グラフやチャートで直感的に把握できる仕組みがあると、課題の発見が格段に早くなります。
- 時系列での変化把握
- 一度の調査だけではなく、半年ごと・年ごとにどう変化しているのかを追えると、施策の効果検証が可能になります。部署や職種ごとの推移を見れば、改善が進んでいるチームとそうでないチームの違いも明らかになります。
- 多角的な分析
- 部署別・年次別・雇用形態別など、さまざまな切り口でデータを分けて見られると、課題の「本当の原因」に近づきやすくなります。例えば「若手社員は満足度が高いのに、中堅社員は低い」といった構造的な問題も見えてきます。
- ベンチマーク比較
- 自社の数値だけを見ても、それが高いのか低いのか判断がつきにくいものです。同業界や市場平均と比較できると、自社の立ち位置を正しく把握しやすくなります。
- 改善施策の提案
- 分析結果を提示するだけでなく、「この課題にはこんな改善が有効」といった具体的なアクションの方向性が示されると、現場で動きやすくなります。
分析機能の充実度が高い調査を選ぶことで、集めたデータを「そのままの情報」ではなく、「実際の組織改善に直結する知見」へと変換できます。これは調査を導入する上で、最も大きな価値といえるでしょう。
4.結果の活用支援
エンプロイー・サーベイ(ES調査)を実施するうえで、最大のポイントは「調査結果をどれだけ実務に活かせるか」です。データを集めること自体は比較的容易ですが、その数値やコメントを具体的なアクションにつなげられなければ、導入効果は半減してしまいます。そのため、結果をどう活用できるかを支援してくれる仕組みがあるかどうかが重要です。
- フィードバック体制の充実
- 調査結果を全社単位でまとめて確認できるのはもちろん、部署別・チーム別に分解して閲覧できるかどうかは、改善活動を現場レベルに落とし込むための鍵となります。管理職やリーダーが自分のチームの状況を把握できる環境があることで、改善行動がスピーディに進みます。
- 改善施策の提案
- 単に「課題がある」と示すだけでは不十分です。課題を抽出し、どのテーマから取り組むべきか優先順位付けを支援してくれる機能があれば、現場で迷うことなく行動に移せます。ベストプラクティスを提示してくれるサービスであれば、より効果的です。
- マネージャー支援機能
- 部署別の結果をもとに、1on1やチームミーティングでの議題に活用できるような仕組みがあると、マネージャーが部下との対話に役立てやすくなります。現場のリーダーが「どう声をかければよいか」「どのテーマを話し合うべきか」といった迷いを軽減できる点も大きなメリットです。
- 継続的な改善サイクルの支援
- 一度の調査で終わらず、次回調査や簡易パルスサーベイにつなげられる設計になっているかも重要です。調査から改善、再調査というサイクルを継続できることで、組織の成長を定量的に確認し、取り組みを積み上げていくことができます。
5.導入・運用のしやすさ
エンゲージメントサーベイを長期的に効果的に活用するためには、導入の簡単さや日常的な運用のしやすさが大きなポイントになります。
せっかく調査を始めても、設定や運用が複雑だと担当者の負担が増え、継続が難しくなるからです。
- 導入の簡単さ 初期設定や設計が直感的にできるかどうかは、スムーズな立ち上げに直結します。専門的な知識がなくても操作できるか、また必要に応じてベンダーからの初期サポートがあるかどうかを確認しておくと安心です。
- 運用のしやすさ 日常の調査運用を効率化するためには、自動化機能(リマインド配信、結果集計など)の有無が大きな助けになります。また、従業員がどの環境からでも回答できるよう、PCやスマートフォンなど複数デバイスへの対応も重要です。
- 継続運用の設計 調査は一度で終わるものではなく、データを蓄積しながら改善に活かしていくことに意味があります。そのため、過去データとの比較が容易にできる仕組みや、結果を分析・活用するためのサポート体制が整っているかどうかも、導入時に見ておきたいポイントです。
6.コスト・契約形態
従業員満足度調査サービスを選ぶ際には、価格の安さだけでなく「どのような料金体系か」「契約形態は柔軟か」を確認することが大切です。
費用対効果を正しく把握することで、無理なく継続的に活用できるサービスを選べます。
- コスト構造の確認 多くのサービスは「従業員数に応じた課金」や「設問数や実施頻度による追加費用」で料金が決まります。たとえば、月1回の調査と年1回の調査では大きなコスト差が生じるケースもあります。自社の調査頻度や規模に合わせて、最適な料金体系を見極めることが重要です。
- 契約形態の柔軟性 年間契約で安くなるサービスもあれば、利用状況に応じて支払える従量課金型もあります。短期的にトライアルしたいのか、長期的に全社導入したいのかによって、適した契約形態は異なります。契約期間や更新条件を事前に確認しておくと安心です。
- 費用対効果の判断 単に「料金が安いかどうか」で決めるのではなく、分析機能の充実度や改善施策の支援、日常的な運用のしやすさといった点も含めて判断することが大切です。初期費用が多少かかっても、結果的に改善施策につながり、離職防止や生産性向上に貢献できるなら十分に投資効果があるといえます。
7.信頼性・実績
従業員満足度調査を選ぶうえで欠かせないのが「信頼性」と「実績」です。どれだけ多くの回答を集めても、調査そのものに信頼性がなければ、得られるデータの精度や活用価値は大きく下がってしまいます。
また、ベンダーの実績が乏しい場合、改善につながる具体的な支援や事例の提供が受けられず、調査結果を“やりっぱなし”にしてしまうリスクもあります。
信頼性と実績を見極める際のポイントは以下のとおりです。- 調査の信頼性
- 設問が理論や学術的根拠に基づいて設計されているか。心理学や組織行動学の知見を取り入れているかどうかは、回答の正確性に直結します。
- 提供ベンダーの実績
- 導入企業の数や業界の幅だけでなく、導入後の支援体制や改善事例が豊富かどうか。単なるアンケート配信ではなく、改善を伴走支援してくれるベンダーかを確認することが重要です。
- 導入効果の可視化
- 従業員満足度の向上や離職率の改善など、実際の成果につながった事例が公開されているか。数字や事例で効果を確認できる調査は、安心して導入できます。
信頼性と実績がしっかり担保された調査を選ぶことで、従業員の本音を確実に把握でき、さらにそこから得たデータを組織改善に直結させることが可能になります。
調査の導入はゴールではなく、改善へのスタートラインです。その意味で「どの調査を選ぶか」は、今後の組織の成長を大きく左右するといえるでしょう。
主要な従業員満足度調査(ES調査)の比較一覧
各サービスの特徴は、2025年10月時点のものです。
アップデート等により、内容が変わっている可能性がありますので、公式サイト等から最新の情報をご確認ください。
ミツカリエンゲージメント(株式会社ミツカリ)
ミツカリエンゲージメントは、従業員満足度を科学的に測定し、組織の課題を可視化するクラウド型の調査ツールです。JSS(Job Satisfaction Survey)という学術理論に基づいて、給与、職場環境、上司や同僚との関係性、業務適性への満足度など、従業員が日々感じている“本音”を網羅的に収集。部署別・年代別・職種別の分析も可能で、現場の課題を具体的に把握できます。
また、調査結果はグラフやダッシュボードで直感的に可視化されるため、人事担当者や経営層でも理解しやすく、改善施策にすぐ活用可能です。マネージャー向けの提案機能や改善アクションのサポートも充実しており、調査結果を組織改善に直結させることができます。 さらに、ミツカリエンゲージメントは短時間で回答できる設問設計とPC・スマートフォン対応で、従業員の回答率向上にも配慮。定期的な調査運用により、組織の変化を追跡しながら、離職防止や働きがい向上につなげることができます。
多くの企業で導入されており、例えば、ソフトバンク株式会社、ヤフー株式会社、ネスレ日本株式会社、マルハニチロ株式会社、株式会社船井総合研究所など、さまざまな業界・組織での導入実績があります。
参考URL:https://mitsucari.com/services/engagementリアルワン従業員満足度調査(リアルワン株式会社)
リアルワン株式会社が提供する「リアルワン従業員満足度調査」は、社員の働きがいや職場環境に対する満足度を可視化し、離職防止や組織改善に役立てられる調査サービスです。従業員が抱える不満や課題を早期に把握できるため、人事施策の優先順位付けやマネジメント改善の根拠データとして活用できます。
また、調査設計から分析レポートの提供まで一貫してサポートしており、調査後の改善アクションにつなげやすい点も特徴です。特に、中小企業から大企業まで幅広く導入されており、従業員満足度調査を初めて導入する企業にも適したサービスといえます。
参考URL:https://www.realone-inc.com/service/es/ES-Quick(NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社)
ES-Quickは、NTTコム オンラインが提供する従業員満足度調査サービスです。短時間で回答できるシンプルな設問設計により、従業員の本音を効率的に収集できます。回答データは自動的に集計・分析され、部門ごとの傾向や課題を即座に可視化できる点が特徴です。
また、NTTグループの豊富な調査ノウハウを活かした設計により、信頼性の高いベンチマークデータとの比較も可能。初めて従業員満足度調査を導入する企業から、既存の調査を改善したい企業まで幅広く活用されています。シンプルさとスピード感を重視する企業におすすめの従業員満足度調査サービスです。
参考URL:https://www.nttcoms.com/service/es/esquick/Niser(ナイサー)ES(公共財団法人 日本生産性本部)
Niser(ナイサー)ESは、従業員満足度やエンゲージメントを科学的に可視化できる従業員サーベイです。心理学や組織行動論に基づいた調査設計により、従業員のモチベーションや定着率に直結する要因を的確に測定できます。結果はわかりやすいレポート形式で提示され、課題の特定から改善施策の立案まで一貫して支援可能です。
また、Niser ESは業種や企業規模を問わず導入でき、従業員の声を経営改善に活かしたい企業に適しています。従業員満足度を継続的に高めたい企業や、人材定着率の向上を目指す人事部門におすすめのサービスです。
参考URL:https://www.jpc-net.jp/consulting/mc/diagnosis_tools/niser/モチベーションクラウド(株式会社リンクアンドモチベーション)
モチベーションクラウド(Motivation Cloud)は、株式会社リンクアンドモチベーションが提供する従業員満足度調査および組織改善支援のクラウドサービスです。国内最大級のデータベースを活用し、従業員の「期待度」と「満足度」を軸に組織の現状を可視化します。
本サービスは、従業員満足度調査(Employee Satisfaction Survey)を通じて、組織の課題を明確化し、改善アクションの立案から実行までを支援します。パルスサーベイやeNPSなど、多様な調査手法を組み合わせることで、定期的な組織状態の把握とPDCAサイクルの構築が可能です。また、部門別・階層別の分析や他社比較機能も備えており、データドリブンな組織改善を実現します。
さらに、モチベーションクラウドは、調査結果をもとにした改善アクションの提案や、マネージャー向けの支援機能を提供し、現場での実践を促進します。これにより、組織のエンゲージメント向上や離職率の低減など、実務成果に直結する効果を期待できます。
参考URL:https://www.motivation-cloud.com/function/engagement-surveyGeppo(株式会社リクルート)
Geppo(ゲッポウ)は、株式会社リクルートとサイバーエージェントの共同開発による、従業員満足度調査に特化したHRサーベイツールです。このサービスは、毎月数問の簡易な質問を通じて、従業員のエンゲージメントやコンディションを定期的に把握することができます。
多くの企業で導入されており、継続率は98%以上を誇ります。例えば、日産自動車株式会社、NTT DATA、株式会社レオパレス21、日清食品ホールディングスなど、さまざまな業界・組織での導入実績があります。
Geppoは、従業員満足度の向上や離職率の改善、オンボーディングの成功など、人事業務の効率化と効果的な組織改善を支援するツールとして、多くの企業に価値を提供しています。
参考URL:https://www.geppo.jp/バヅクリエンゲージメント(株式会社バヅクリ)
株式会社バヅクリが提供する「バヅクリエンゲージメント」は、従業員満足度調査とオンラインワークショップを組み合わせた独自のサービスです。単なるアンケート型の従業員満足度調査にとどまらず、調査結果をもとにチームビルディングやコミュニケーション活性化の施策を実行できる点が特徴です。
調査では従業員のエンゲージメント状態や職場満足度を可視化し、オンラインイベントを通じて改善アクションを実践。離職防止や組織力の向上につなげられます。特に、在宅勤務やハイブリッドワーク環境での従業員のつながり不足に課題を持つ企業に適しており、「従業員満足度を測るだけでなく、改善まで実現したい」と考える人事担当者から支持を集めています。
参考URL:https://hr.buzzkuri.com/engagementアッテルサーベイ(株式会社アッテル)
アッテルサーベイは、従業員満足度を可視化し、組織改善に直結するアクションを導き出す従業員満足度調査サービスです。従業員の声を「満足度スコア」として定量的に把握できるだけでなく、分析結果をもとに離職リスクやモチベーション低下の要因を特定し、改善施策に活用できます。
また、アッテルサーベイは人材データを活用した科学的アプローチを得意としており、組織の現状を把握するだけでなく、配属や採用といった人材マネジメント領域との連携も可能です。従業員満足度を測るだけにとどまらず、企業の生産性向上や人材定着に貢献する調査サービスとして、多くの企業から注目を集めています。
従業員満足度を継続的にモニタリングし、データに基づいた組織改善を実現したい企業におすすめです。
参考URL:https://attelu.jp/surveyミキワメウェルビーイング(株式会社リーディングマーク)
ミキワメウェルビーイングは、株式会社リーディングマークが提供する従業員満足度調査サービスで、従業員の心理的状態や働きがいを可視化し、組織改善につなげることができます。定期的なサーベイにより、ストレスや不調の兆候を早期に把握し、離職やパフォーマンス低下を未然に防ぐサポートが可能です。
また、従業員のウェルビーイングに着目した設計で、エンゲージメントだけでなく、健康・幸福感・働きやすさといった多面的な観点から分析できる点が特徴です。管理画面では結果が見やすく整理され、組織全体・部署単位での課題抽出や改善施策の立案に役立ちます。
従業員の声を継続的に把握し、科学的データに基づいた人事施策を推進したい企業におすすめの従業員満足度調査サービスです。
参考URL:https://mikiwame.com/well-being.htmlラフールサーベイ(株式会社ラフール)
ラフールサーベイは、株式会社ラフールが提供する従業員満足度調査サービスで、従業員のメンタルヘルスやストレス状況を可視化できる点が大きな特徴です。一般的な従業員満足度の把握だけでなく、心理的安全性やエンゲージメント、健康リスクなど多角的な視点から社員の状態を分析できます。
結果に基づいた具体的な改善アクション提案や、組織課題を早期に発見する仕組みも備わっています。メンタル不調や離職リスクを未然に防ぎたい企業、従業員のパフォーマンス最大化を目指す企業に最適な従業員満足度調査サービスといえます。
参考URL:https://survey.lafool.jp/SmartHR 従業員サーベイ(株式会社SmartHR)
SmartHR 従業員サーベイは、株式会社SmartHRが提供する従業員満足度調査サービスです。人事労務クラウド「SmartHR」とシームレスに連携できる点が大きな特長で、従業員データをもとに組織の状態を効率的に可視化できます。
アンケート形式で社員の意識や職場環境に対する満足度を測定し、ストレスや離職リスクの把握にも活用可能です。調査結果はダッシュボードで分かりやすく表示され、改善施策の検討にも直結します。既にSmartHRを利用している企業はもちろん、従業員満足度の向上と人事データの一元管理を同時に実現したい企業におすすめのサービスです。
参考URL:https://smarthr.jp/function/survey/カオナビ(株式会社カオナビ)
カオナビは、株式会社カオナビが提供するタレントマネジメントシステムで、従業員満足度調査にも対応可能なクラウドサービスです。人材情報を一元管理しながら、パルスサーベイや従業員アンケートを通じて従業員満足度やエンゲージメントを可視化できます。
組織や部署ごとの傾向を分析することで、離職防止やマネジメント改善にも役立ちます。シンプルで直感的な操作性が特徴で、導入実績も豊富。人事評価や人材育成とあわせて、従業員満足度調査を効率的に実施したい企業におすすめのサービスです。
参考URL:https://www.kaonavi.jp/func/voicenote/HRBrain 組織診断サーベイ(株式会社HRBrain)
HRBrainが提供する「組織診断サーベイ」は、従業員満足度やエンゲージメントを可視化できるクラウド型の従業員満足度調査ツールです。
独自のサーベイ設計により、モチベーションや心理的安全性、マネジメント課題などを定量的に把握可能。回答結果はリアルタイムで集計・分析され、組織課題の抽出から改善施策の立案までをスピーディーに支援します。人事評価やタレントマネジメント機能とも連携できるため、従業員満足度調査を単発で終わらせず、人材育成や離職防止につなげたい企業に最適です。
参考URL:https://www.hrbrain.jp/employee-experience従業員満足度調査を成功させるためのポイント
従業員満足度調査(ES調査)は、実施するだけでは十分な効果は得られません。重要なのは、調査で得た結果をどのように現場へ落とし込み、改善につなげるかです。成功させるためには、以下のポイントを意識することが大切です。1. 回答率を高める仕組みを作る
従業員満足度調査は、できるだけ多くの従業員から回答を集めることで、組織の実態を正しく把握できます。しかし、回答率が低いと偏った意見に基づく分析となり、改善施策に誤りが生じてしまう可能性もあります。そのため、回答率を高める仕組みを設計することが重要です。
そして、回答率を高めるためには、まず負担の少ない設問設計を行うことが欠かせません。設問数が多すぎたり、回答に時間がかかりすぎたりすると、従業員の参加意欲は下がってしまいます。短時間で回答できるシンプルな設計を意識し、気軽に取り組めるボリュームに調整することが効果的です。
次に、回答環境の整備も重要です。PCだけでなくスマートフォンやタブレットからもスムーズに回答できる仕組みを用意することで、現場や移動中の従業員も負担なく参加できます。多様な働き方が広がる中、どの環境からでもアクセスできる利便性が、回答率向上につながります。 さらに、周知とリマインドも欠かせません。調査の実施目的や意義を社内にしっかり伝え、従業員が「自分の声が会社に反映される」と実感できるようにすることが大切です。加えて、回答期限前にリマインドを行い、参加を促すことで未回答者を減らすことができます。
このように「設問設計」「回答環境」「周知・リマインド」の3つをバランスよく整えることで、回答率を高め、より信頼性の高いデータを収集できるようになります。
2. 結果を可視化し、分かりやすく伝える
従業員満足度調査のデータは、そのままでは現場や経営層に伝わりにくく、改善アクションにつなげにくいことがあります。人事担当者としては、誰がどの課題を抱えているかを一目で把握できる形で提示することが重要です。
まずは 部署別・年代別・上司別など、複数の切り口でデータを比較できる形式にすることで、課題の傾向や重点的に改善すべき対象を特定しやすくなります。たとえば、特定の部署や年代で低評価が集中している場合、その原因を掘り下げて対応策を検討できます。
次に、数値だけでなく グラフやチャート、ダッシュボードを活用して可視化することがポイントです。棒グラフや折れ線グラフでトレンドを示したり、部署ごとのスコアを色分けして表示するだけで、現場のマネージャーや経営層も直感的に理解でき、改善の優先順位を決めやすくなります。 さらに、分析結果を現場に落とし込む形式にすることで、マネージャーや担当者が具体的な改善行動を計画しやすくなります。単なる数値報告ではなく、「どの部署のどの項目に注意すべきか」「改善の優先順位はどこか」を明示することで、調査結果を組織改善に直結させることが可能です。
このように、比較可能な切り口+視覚的な可視化+現場での活用イメージをセットで提供することが、人事担当者にとって最も有効な結果の伝え方と言えます。
3. 改善アクションにつなげる
従業員満足度調査は、データを集めるだけでは意味がありません。人事担当者として重要なのは、調査結果を現場の改善アクションにつなげることです。
まず、調査結果を分析したうえで、具体的な改善策や行動計画に落とし込むことが必要です。たとえば、部署別のスコアを確認し、低評価が目立つ領域に対しては改善目標を設定します。「業務負荷が高い部署には業務分担の見直しを行う」「コミュニケーション不足が課題の部署には定期的な1on1やチームミーティングを導入する」といった具体策です。 さらに、マネージャーに対しては 「どの部署でどのような声かけが有効か」や「改善優先度の高い項目はどれか」 などの提案をセットで提供することがポイントです。マネージャーが自部署の課題を理解しやすくなることで、日常業務の中で即実践できる改善行動につながります。
また、改善アクションを推進する際には、効果の見える化も同時に行うことが大切です。実施後に再調査や簡易チェックを行い、改善策が実際に従業員満足度に反映されているかを確認することで、PDCAサイクルを回しながら組織改善を加速できます。
つまり、調査結果の分析 → 具体的改善策の策定 → マネージャーへの提案 → 実施 → 効果検証 の一連の流れを設計することが、従業員満足度調査を組織改善に直結させるカギとなります。
4. 継続的な運用で変化を追う
従業員満足度調査は、一度実施して終わりでは意味がありません。組織の状態は時間とともに変化するため、定期的に調査を繰り返し行うことで、従業員の意識や職場環境の変化を追跡することが重要です。
具体的には、四半期や半年ごとに簡易調査(パルスサーベイ)を実施し、部署別や年代別のスコアをモニタリングします。こうすることで、改善施策の効果をリアルタイムで把握し、必要に応じて軌道修正が可能になります。
また、調査結果と改善策をセットで確認することがポイントです。例えば、「この部署では改善施策を実施したが、スコアは上昇したか」「他部署に影響が出ていないか」といった観点で分析すると、PDCAサイクルが効果的に回せます。 人事担当者としては、継続的なデータ取得と改善アクションのセット運用により、組織全体の従業員満足度を着実に向上させることが可能です。これにより、施策の成果が目に見える形で確認でき、現場への説明や経営層への報告もスムーズになります。
5. 自社の課題に合わせてサービスを選ぶ
従業員満足度調査の導入を成功させるには、自社が抱える具体的な課題に適したサービスを選ぶことが重要です。たとえば、離職率の高さが課題であれば、離職リスクを可視化できる設問や分析機能が充実したサービスを選ぶ必要があります。組織文化の把握や職場環境の改善を重視する場合は、部署別・年代別の比較や自由記述を活かした分析ができるサーベイが適しています。また、マネジメント支援を目的にする場合は、チーム単位での課題把握やマネージャー向けの改善アクション提案が含まれているサービスを選ぶと現場での活用がスムーズです。
さらに、導入支援や分析サポートが充実しているサービスを選ぶことで、人事担当者の負担を減らしながら、現場に定着させやすくなります。たとえば、初期設定のサポートや分析レポートの作成支援、改善施策の提案があるサービスであれば、調査結果をそのまま現場改善に直結させやすく、PDCAサイクルをスムーズに回すことが可能です。
つまり、自社の課題 × サーベイの強みを照らし合わせ、トライアルやデモを通じて操作感や活用のしやすさを確認することが、調査を実務で最大限に活かす第一歩となります。
自社に合ったエンゲージメントサーベイを選ぶポイント
従業員満足度調査(ES調査)は、ただ導入して数値を集めるだけでは意味がありません。調査結果をどう解釈し、実際の改善行動に落とし込むかまで設計してこそ、従業員の定着率向上やモチベーション改善といった成果につながります。
まず大切なのは、自社の課題や目的を明確にすることです。例えば
- 離職防止を重視したい
- 「給与・福利厚生」や「上司との関係性」を測る調査が有効
- 組織文化や働きやすさを見える化したい
- 職場環境や心理的安全性を捉える調査が適切
- マネジメント強化につなげたい
- 部署ごとやマネージャー別の比較分析が可能なサービスが役立つ
目的次第で、適した調査の種類や設問設計、運用の仕方が変わってきます。
次に、サービス選定の際にチェックすべき観点を整理してみましょう。
- 回答のしやすさ
- 設問数や回答時間が適切で、PC・スマホなどからスムーズに回答できるか
- 分析・可視化機能
- 部署別や年代別の比較、時系列での変化把握など多角的な分析が可能か
- 改善行動への支援
- 結果を踏まえた改善提案や、マネージャー向けアクションプランが用意されているか
- 導入・運用サポート
- トライアルや伴走支援があり、現場に定着しやすい仕組みか
- コスト感・規模感
- 自社の従業員規模や実施頻度に合った料金体系か
さらに、調査は一度実施して終わりにせず、定期的に繰り返すことで初めて意味を持ちます。回答率を高める工夫を行い、結果をわかりやすく可視化し、改善サイクルを回す。この継続プロセスによって、従業員満足度を持続的に高めることができます。
最後に、導入前には必ず 「自社の課題 × サービスの強み」 を照らし合わせましょう。トライアルやデモを通じて、操作感や活用しやすさを事前に確認することが重要です。これにより、調査結果を単なる数値にとどめず、従業員満足度向上や離職防止といった実務成果へと確実につなげることができます。

ミツカリ
会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ
5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。
特集
- 性格適性検査
- エンゲージメントサーベイとは
- 適職診断
- エンゲージメント
- 従業員満足度
- ワークエンゲージメント
- サーベイの質問項目
- サーベイは無駄!?
- サーベイのデメリット
- サーベイの選び方
- 匿名・実名
- エンゲージメントサーベイ事例
- ミツカリエンゲージメント
- ミツカリ適性検査
- 『エンゲージメント』とは?
- 適性検査を徹底比較
- 従業員満足度とコミュニケーション
- 従業員満足度と報酬
- 従業員満足度と人間関係
- 従業員満足度と業務適性
- ワークエンゲージメント測定方法
- ワークエンゲージメント高め方
- エンゲージメントサーベイ比較
- 従業員エンゲージメントとは?
- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション
- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説
- ワークエンゲージメントとバーンアウト
- ワークエンゲージメントとストレスチェック
- ワークエンゲージメント事例
- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?
- 従業員エンゲージメントを高めるには?
- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?
- 従業員満足度調査は意味ない?
- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説
- 従業員満足度調査おすすめ
特集
- 性格適性検査
- エンゲージメントサーベイとは
- 適職診断
- エンゲージメント
- 従業員満足度
- ワークエンゲージメント
- サーベイの質問項目
- サーベイは無駄!?
- サーベイのデメリット
- サーベイの選び方
- 匿名・実名
- エンゲージメントサーベイ事例
- ミツカリエンゲージメント
- ミツカリ適性検査
- 『エンゲージメント』とは?
- 適性検査を徹底比較
- 従業員満足度とコミュニケーション
- 従業員満足度と報酬
- 従業員満足度と人間関係
- 従業員満足度と業務適性
- ワークエンゲージメント測定方法
- ワークエンゲージメント高め方
- エンゲージメントサーベイ比較
- 従業員エンゲージメントとは?
- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション
- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説
- ワークエンゲージメントとバーンアウト
- ワークエンゲージメントとストレスチェック
- ワークエンゲージメント事例
- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?
- 従業員エンゲージメントを高めるには?
- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?
- 従業員満足度調査は意味ない?
- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説
- 従業員満足度調査おすすめ
これらの記事もあわせて
よく見られています
その他、お客様から評価いただいているポイント
すぐに結果を反映
最小限の受検負荷
現場の方でも使いやすい
貴社に合った人材モデルの作成
業界平均との比較サービス
無料トライアル
改善事例が豊富
高いセキュリティ性
ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など
お役立ち資料をご用意しております

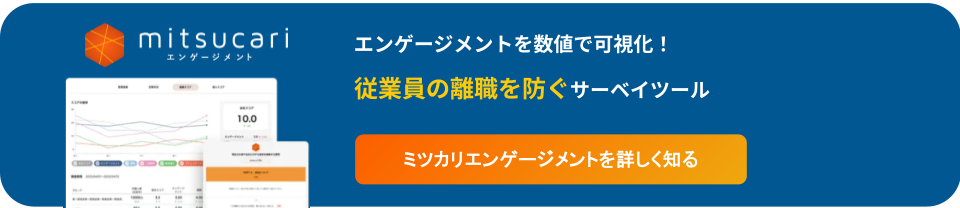






.jpg&w=750&q=75)





