
面接評価基準の設計方法を紹介!新卒・中途別に評価シートの例も
「面接」は、入社後のミスマッチを防ぐためにも評価項目の統一は欠かせません。しかし、以下の悩みを抱える採用担当者は多いのではないでしょうか?
- 面接の評価基準で何を設定すれば良いのかわからない…
- 面接担当者によって評価にバラつきがあり統一したい
当記事では、面接評価シートに欠かせない基本項目はもちろん、面接の段階別での評価項目や点数の付け方、新卒・中途別に評価シートの例などをHRTechツールで採用課題を解決してきた『ミツカリ』が解説します。
面接評価の基準を統一したいと考えている方の参考になれば幸いです。
目次
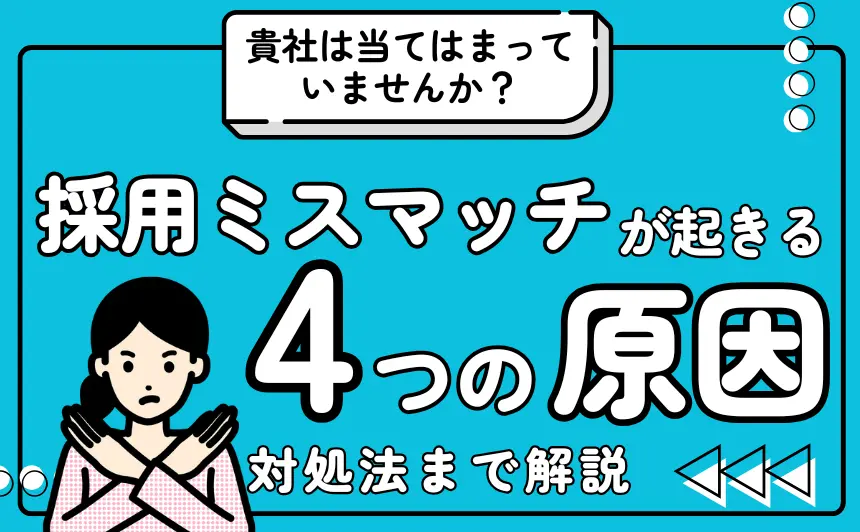
面接官の主観や経験で評価基準が異なると、求める人物像やスキルを適切に評価できず採用後のミスマッチにつながります…。
本資料では、採用候補者を適切に見定められない原因と解決方法を解説しています!
面接の評価基準を設ける重要性
採用業務における課題は数多くありますが、求職者を見極めるためには、面接における評価項目・基準を一致させる必要があります。
リクルートキャリア「就職白書2023」によると、新卒の採用活動として「面接(対面・Web)」を行なっている企業は約90%であることがわかります。

ほぼ全ての企業が実施していることから、面接は採用活動の中でも特に重要なプロセスです。面接の評価基準を定めておくことで「面接官による評価のバラつきを抑える」「入社後のミスマッチを防ぐ」ことにつながります。
面接の評価基準・項目をただ設定するのではなく、評価基準をもとにどの社員が面接を行っても、同じ目線・評価で採用面接を行える状態を構築するとより効果的です。
企業によって求める人物像は異なりますので、人事担当者同士はもちろん採用をかける部署のメンバーとも話し合いながら評価基準・項目を定めていくと良いでしょう。
面接評価基準の設計方法
面接の目的は「書類選考では分からない要素」を評価することです。
応募者の人柄や価値観、コミュニケーション能力などの定性的な要素は、面接官の主観に任せすぎると評価にバラツキが出てしまう危険性があります。求職者を客観的に見極めるためには、具体性の高い評価項目・評価基準を面接評価シートに設計することが大切です。
評価項目や評価基準を具体的にするための方法としては「抽象概念を具体的なスキルに落とし込む」という方法が挙げられます。
面接による求職者の見極めで重要な要素である「コミュニケーション能力」は、抽象性の高い概念であるため、そのままでは客観的な評価が困難です。しかし、コミュニケーション能力を「傾聴力」や「アサーション」などのスキルに細分化することで、客観的な評価が可能になります。
各評価項目を判断するための細分化ができたら、評価項目の優先順位をつけてみましょう。面接の時間は限られているため、重要な項目ほど具体化や優先順位を細かく設定することで、採用フローの効率化につながります。
面接評価シートに欠かせない基本項目
面接評価シートは、採用候補者の能力や振る舞いなどを記録し、面接官同士で客観的な視点から選考や採用の合否を決定するための判断材料として重要なツールです。しかし、面接評価シートにどのような項目を設定するべきか悩んでいる人事担当者も多いと思います。
面接評価シートに入れたい基本的な項目は以下の通りです。
- 知識(一般常識、教養、語学力 など)
- コミュニケーション能力(会話力、伝え方、傾聴力 など)
- 行動力(リーダーシップ、主体性、協調性 など)
- 思考力(論理的思考、創造力、問題発見 など)
- 人間力(ストレス耐性、向上心、価値観 など)
「知識」の評価基準は、SPIや適性検査を導入するのも良いですが、最近の時事ニュースなどを質問するのも効果的です。
「コミュニケーション能力」の評価基準は、面接の中で質問の意図を理解し回答できているか、面接官が話しているときの聞く姿勢などを設定すると良いでしょう。
「行動力」「思考力」の評価基準は学生生活など、具体的なエピソードから聞き出して評価しましょう。
「人間力」の評価基準はストレス解消のための休日の過ごし方や、目標を立てて勉強していることなどを聞くと良いです。性格・価値観、志向性などは面接の中で判断しづらいため、性格適性検査を活用して可視化するとより評価しやすいでしょう。
【例】新卒採用に活用できる面接評価シート
面接の評価シートに欠かせない基本項目をもとに、新卒採用での評価シートを例でつくってみました。チェック項目の数や内容は、自社のカルチャーや求める人物像、募集ポジションなどをもとに調整しましょう。

【例】中途採用に活用できる面接評価シート
中途採用は募集ポジションの経験・スキルがあれば良いと思われがちですが、採用のミスマッチによる早期離職を防止するためにもカルチャーフィットなども考慮した面接評価シートを作成すると良いでしょう。

【面接の段階別】評価基準・項目
2023年卒リクルートの「就職活動・採用活動に関する振り返り調査」によると、採用における平均選考回数は2.4回で「新卒の採用面接は平均2~3回」ということがわかります。

採用戦略を立てる上では、この「2~3回の面接をどう使うか」を考えることが大切です。ここでは、面接の段階ごとにチェックすべき評価基準・項目を解説します。
一次面接の評価基準・項目
- 身だしなみ
- 表情
- 志望動機(入社意欲) など
一次面接は人事担当者が面接を行うケースが多いと思います。そのため、身だしなみや表情といった第一印象、仕事に支障がない程度のコミュニケーション能力があるか、仕事に対する考え方・姿勢といった\意欲を評価基準\として定めると良いでしょう。
二次面接の評価基準・項目
- 成功または失敗体験
- 自己PR
- 主体性
- 傾聴力
- 課題発見力 など
二次面接になると、現場社員を複数人加えての面接になることが多いと思います。「職場環境に合うか」「会社で活躍できるか」といった、求職者と各部署とのカルチャーフィットを見極める評価基準の設定がおすすめです。
最終面接の評価基準・項目
- 新卒者の価値観
- 社風・企業理念とのマッチング など
最終面接は、社長や役員を加えて実施されることが多いです。そのため「一緒に働きたいと思う人物か」という求職者の価値観と理念との相性といった会社全体とのカルチャーフィットを見極める評価基準を設定すると良いでしょう。
最終面接では「徐々に抽象度の高い要素に踏み込んでいくこと」と「能力から人柄に視点を移していくこと」が基本です。
必ずしも上記の順番で行うべきというわけではありませんが、採用においてどんなことを重視するか、企業の価値観や採用目的に合わせて適宜変更を加えて「自社独自の採用評価・基準」を考案することが大切です。
効果的な面接を行うためには、自社独自の採用プロセスを考案した上で、どのようなスキルを見極めるのか、どのような性格・価値観やコンピテンシーを見極めるのかなどを、採用要件定義から具体的に落とし込むことが重要です。
面接の評価・点数の付け方
面接の評価・点数の付け方には、おおきくわけると「加点方式」「減点方式」「段階評価」の3つがあります。自社の面接体制や選考段階によって、どの方式にするのかを決めると良いでしょう。
加点方式
加点方式は「0点から点数を加算する方式」です。
求められるスキルや資質など採用候補者のポジティブな要素に注目して評価・ポイントを加算します。そのため、応募者からも好感をもちやすく、入社意欲が高まる効果も期待できるという特徴があります。
減点方式
減点方式は「100点から点数を引いていく方式」です。
採用候補者の欠点や評価などが望ましくない場合にポイントを減算します。例えば、質問に対する回答が不適切であったり、マナーに欠けた場合などにポイントが減点されます。
減点要素を探すために、圧迫面接になりやすいという特徴があります。採用候補者の入社意欲や企業イメージがさがる可能性があるため、加点方式か減点方式で悩んだ際は「加点方式」を採用すると良いでしょう。
段階評価
段階評価は以下いずれかの方式で採用候補者の合否を判断します。
- 言葉による評価(「非常に良い」「良い」「どちらでもない」「やや悪い」「悪い」)
- 数字による評価(1~3段階、1~5段階 など)
- アルファベットによる評価(「S」「A」「B」「C」「D」など)
段階評価の場合は「○○の項目が低い場合は不採用」「「C」や「D」が〇個以上の場合は不採用」など評価基準を決めておきましょう。また、他の採用候補者と比較して印象や回答が良かった場合は特例で「SS」をつけるなどのルールもあると、採用候補者を公正に判断できます。
採用候補者の評価点数が同じになる可能性もあるので、その場合は「○○の項目の点数が高い方」なども決めておくと良いでしょう。
面接の評価を有効に活用する方法
面接評価シートは合否判断だけでなく、他にも有効に活用する方法があります。ここでは面接の評価を有効に活用する方法を2つ紹介します。
「見極め」に活用する
採用面接において、応募者の「コミュニケーション能力」は特に重要です。
経団連の調査によると、選考時に「コミュニケーション能力」の要素が長期間にわたり優先されており、多くの企業がコミュニケーションスキルの見極めを面接の目的としていることがわかります。

出典元『経団連』2018年度 新卒採用に関するアンケート調査結果
ただし、コミュニケーション能力を重視する上で注意したいのは、あくまでも「企業側の視点」であるということです。採用担当者が応募者の見極めを行っているのと同時に、応募者も企業の見極めを行っています。このバランスが求職者と企業の双方にとって重要になってきます。
HRproに掲載されている調査では「面接官の印象で志望度に影響した」と答える新卒者は文系・理系ともに8割を超えています。不誠実な対応や適応できない状況が、逆に志望度を下げ選考を辞退する要因となります。

出典元『HRpro』「面接官の印象が企業に対する志望度に影響したか」について
「口説き」に活用する
「口説き」もまた重要な要素です。求職者が面接で企業を評価するように、企業も積極的に求職者を口説く必要があります。適切でない対応や不誠実な態度は、優れた人材が内定を辞退する可能性を高めます。
将来的に社員として働いてもらう方や潜在的な顧客としての価値を考え、面接官の態度や対応には特に気を配る必要があります。企業が内定を出しても、選考辞退のリスクがあるため、誠実な対応と積極的なアプローチが重要です。
「構造化面接」による面接手法・評価基準の統一
面接の評価をより客観的・効率的に行うための方法として、Googleが採用している「構造化面接」という面接手法があります。
構造化面接とは、臨床心理学におけるアプローチの1つで「あらかじめ評価基準と質問項目を決めておき、マニュアル通りに実施していく」という面接手法です。面接の評価結果が属人化せず、統一感のある採用選考が可能になる効果が期待できます。
構造化面接による面接手法の統一を検討する際に利用価値が高いのが「適性検査」などの既存ツールです。適性検査を事前に応募者全員に受けてもらうことで、応募者の価値観と会社の社風との距離を面接前に見極めることができます。
面接の手法を統一することで、面接で「見極め」ばかりに気をとられる心配がなくなります。面接の目的は「見極め」だけでなく「口説き」もありますので、面接の場で応募者の価値観や考え方を理解した上で、自社だからできることなどの他社との差別化要因を説明できるようになります。
面接では求職者はもちろんのこと、面接官も緊張します。書類選考や適性検査によって事前に求職者の人物像を把握しておけば、面接の効率化だけでなく面接官の緊張をやわらげることができ、求職者を「口説き」やすくなることにもつながります。
採用候補者の人柄・価値観を可視化するHRTechツール

面接で適切に評価するには、評価シートで基準や項目を設けて人材を見極めることが重要とお伝えしました。しかし、採用候補者本来の性格・価値観・志向を面接で正確に判断するのは難しいのも事実です。
採用候補者本来の人柄や価値観を客観的に判断するには、性格適性検査などの外部ツールの活用が欠かせません。
弊社『ミツカリ』では、適性検査とエンゲージメントサーベイを用いて応募者や既存従業員ひとりひとりの性格や相性を可視化するHRTechサービスを提供しています。
約10分の適性検査で採用候補者の性格・価値観を可視化できます。

面接評価シートの項目・基準に多い「ストレス」「コミュニケーション」「仕事」「行動・活動」「マネジメント」「意思決定」の6つの傾向も以下のように可視化できるので、面接評価シートと併用して採用候補者を評価することも可能です。

また、既存の従業員にも受検いただくことで、採用候補者との相性を確認できます。

既存従業員の性格・価値観を可視化することで、社内の配置転換を検討する際や、部署内にどのような性格・価値観の人材が多いのかも明確にできます。先輩と似た性格の新入社員の配属を決定する場合だけでなく、同様の性格・価値観をもつ先輩をメンターとしてつけたい場合にも活用可能です。
さらに新入社員の入社後は、7問約1分でエンゲージメントサーベイ機能で現状を可視化できます。「社員のワークエンゲージメント」「報酬」「人間関係」「職務適性」「コミュニケーション」の5つの要素から、新入社員の変化をいち早くキャッチできるため、入社後のフォローも迅速に対応可能です。

面接評価設計の改善事例
弊社「ミツカリ」を導入・活用して、面接時の評価やプロセスを改善した事例を1社紹介します。
株式会社ファームノートホールディングス
酪農・畜産向け牛群管理システムの開発。提供を行う株式会社ファームノートホールディングス様の改善事例です。「課題」「ミツカリ導入の理由」「活用結果」の3つにわけて紹介します。
課題
面接官ごとに採用候補者を評価する基準にバラつきがありました。特に社内でも問題視されていたのは「今この瞬間に○○のスキルをもっているか」という遂行能力だけで採用を判断していたことです。
能力だけでなく、人物像や価値観も考慮して人材を採用するために工夫が必要と考えていました。
ミツカリ導入の理由
- グルーピング機能(従業員をグルーピングして採用候補者との相性を比較できる)
- 部署ごとの特徴を可視化できること
- 採用候補者の性格・価値観を可視化して採用を検討できること
結果
能力だけではない人物重視の採用が実現しました。
結果をもとに人柄の想像や、面接での評価内容・質問事項を事前に考えることができるようになり、面接官の意識も大きくかわりました。
>>「株式会社ファームノートホールディングス 様」の導入事例はこちら
面接の評価項目を設けて公正な採用を!
今回は面接の評価に焦点をあてて、設計方法や評価項目などを紹介しました。
面接の評価項目をしっかりと設定して活用すると、面接官ごとに評価がブレることが少なくなります。採用候補者を公正に評価できるため、選考の質が向上し採用活動もスムーズに行えるでしょう。
とはいえ、面接の中だけで採用候補者の人間力(主に性格や価値観、志向性など)を評価するのは非常に難しいです。そのため、人柄重視の評価項目を設定する場合は、採用候補者の性格・価値観を客観視できる性格適性検査などのツールを活用すると良いでしょう。
弊社『ミツカリ』では、採用候補者や既存従業員の性格・価値観を可視化する性格適性検査とエンゲージメントサーベイを用いたHRTechサービスを提供しています。
約10分の適性検査を受検することで、採用候補者の性格・価値観を可視化できます。結果シートは誰が見ても理解できるように設計されているため、面接評価シートと比較しながら採用候補者の合否を決めることが可能です。
現在、14日間の無料トライアルも実施中ですので、ぜひこの機会にご検討いただけますと幸いです。

ミツカリ
会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ
5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。
特集
- 性格適性検査
- エンゲージメントサーベイとは
- 適職診断
- エンゲージメント
- 従業員満足度
- ワークエンゲージメント
- サーベイの質問項目
- サーベイは無駄!?
- サーベイのデメリット
- サーベイの選び方
- 匿名・実名
- エンゲージメントサーベイ事例
- ミツカリエンゲージメント
- ミツカリ適性検査
- 『エンゲージメント』とは?
- 適性検査を徹底比較
- 従業員満足度とコミュニケーション
- 従業員満足度と報酬
- 従業員満足度と人間関係
- 従業員満足度と業務適性
- ワークエンゲージメント測定方法
- ワークエンゲージメント高め方
- エンゲージメントサーベイ比較
- 従業員エンゲージメントとは?
- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション
- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説
- ワークエンゲージメントとバーンアウト
- ワークエンゲージメントとストレスチェック
- ワークエンゲージメント事例
- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?
- 従業員エンゲージメントを高めるには?
- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?
- 従業員満足度調査は意味ない?
- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説
- 従業員満足度調査おすすめ
これらの記事もあわせて
よく見られています
その他、お客様から評価いただいているポイント
すぐに結果を反映
最小限の受検負荷
現場の方でも使いやすい
貴社に合った人材モデルの作成
業界平均との比較サービス
無料トライアル
改善事例が豊富
高いセキュリティ性
ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など
お役立ち資料をご用意しております













